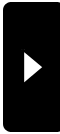災害に備える一年に
2020年01月07日
あけましておめでとうございます。
振返れば、昨年は大型台風の被害に見舞われた一年でした。
わずかにコースが逸れたことで、遠州地方では大きな被害はなかったものの、長野や東日本では大変な災害になったことは記憶に新しいところです。

(台風19号の被害:千曲川)
地球温暖化の影響なのか、台風は以前よりも格段に増え、規模も大きくなっています。
賃貸管理会社として、「いざ」という時に入居者の安全と、建物の資産価値を守れる会社でありたいと思います。
そのために、防水補修など、オーナー様に事前の建物メンテナンスを提案することも、我々の責任だと感じてます。
大きな災害がないことを願いつつ、しっかりと「万が一」に備えていく一年にしてまいります。
本年もよろしくお願いします。
振返れば、昨年は大型台風の被害に見舞われた一年でした。
わずかにコースが逸れたことで、遠州地方では大きな被害はなかったものの、長野や東日本では大変な災害になったことは記憶に新しいところです。

(台風19号の被害:千曲川)
地球温暖化の影響なのか、台風は以前よりも格段に増え、規模も大きくなっています。
賃貸管理会社として、「いざ」という時に入居者の安全と、建物の資産価値を守れる会社でありたいと思います。
そのために、防水補修など、オーナー様に事前の建物メンテナンスを提案することも、我々の責任だと感じてます。
大きな災害がないことを願いつつ、しっかりと「万が一」に備えていく一年にしてまいります。
本年もよろしくお願いします。
今年も「改善活動発表会」を開催しました
2019年12月04日
昨年に引き続き、今年も12月3日に「アライブ改善活動発表会」を開催しました。
※昨年の様子はこちら
https://www.your-alive.co.jp/president/2019/01/
昨年以上にレベルの高い発表ばかりで、アライブのスタッフの改善マインドがますます高まっていることを強く感じました。

おかげさまで、今年は昨年以上に賃貸管理のご相談を多くのオーナー様から頂いており、うれしい悲鳴を上げています。
日に日に増えていく賃貸物件をしっかりと管理・運営するには、限られた時間をより効率よくに使うために、仕事のやりかたを繰り返し見直す必要があります。
********
・トップダウン方式による「マニュアルの精度と実行の徹底性」で勝負するのは、専業化した全国大手企業のやりかた
・アライブのような「地域密着・多角化」企業では、ボトムアップ方式で「現場の創意工夫を仕事に反映させる」柔軟性こそが高い成果につながる
********
と確信しています。

そして、「改善マインドの盛り上げ役」は社長であるわたしの最重要の仕事のひとつだと考えてます。
アライブみんなの創意工夫で、お客様にさらに良いサービスを提供してまいります!
※昨年の様子はこちら
https://www.your-alive.co.jp/president/2019/01/
昨年以上にレベルの高い発表ばかりで、アライブのスタッフの改善マインドがますます高まっていることを強く感じました。
おかげさまで、今年は昨年以上に賃貸管理のご相談を多くのオーナー様から頂いており、うれしい悲鳴を上げています。
日に日に増えていく賃貸物件をしっかりと管理・運営するには、限られた時間をより効率よくに使うために、仕事のやりかたを繰り返し見直す必要があります。
********
・トップダウン方式による「マニュアルの精度と実行の徹底性」で勝負するのは、専業化した全国大手企業のやりかた
・アライブのような「地域密着・多角化」企業では、ボトムアップ方式で「現場の創意工夫を仕事に反映させる」柔軟性こそが高い成果につながる
********
と確信しています。

そして、「改善マインドの盛り上げ役」は社長であるわたしの最重要の仕事のひとつだと考えてます。
アライブみんなの創意工夫で、お客様にさらに良いサービスを提供してまいります!
静岡大学と浜松医科大学の合併について
2019年11月01日
静岡大学浜松キャンパスと浜松医科大学が合併して「浜松医科工科大学」に改称するというニュース、お読みになった方も多いと思います。
https://www.at-s.com/news/article/topics/shizuoka/675661.html
「情報学部の存在感が薄れてしまう」などの理由で反対の声もあるそうです。たしかに、理解できるところです。
浜松キャンパス学生物件、地域シェアNO.1のアライブとしても、気になるニュースです。

合併推進派の静岡大学石井学長が、個人ブログで合併について詳細に説明しています。
https://wwp.shizuoka.ac.jp/president-blog/
非常にストレート、また論理的で丁寧な説明で、このブログ全体を通して、石井学長の合併に賭ける熱意と誠意が伝わってきます。
関心のあるかたは是非直接読んでいただきたいのですが、かなりの長文なので、私の理解なりに、要約します。
*******************
・浜松医科大学と静岡大学が合併して医学部を含む総合大学となることは、教育の多様性や大学運営上の財政面で大きなメリットがある。
・2000年に全学部共通の教養課程が廃止されて以降、静岡キャンパスと浜松キャンパスは事実上別々の大学として機能しており、学生間の交流は少ない。合併により静岡大学ホールディングスの下に「静岡地区大学」と「浜松地区大学」の2大学に再編して、組織の在り方を実際の大学の実情に合わせることは、意思決定の合理化・迅速化につながる。
・合併により、「静岡地区大学」よりも、医学部を含む「浜松地区大学」のほうが財政的・規模的に大きくなるのは事実だが、合併に伴い現状の静岡キャンパスの財政や事業規模が縮小されるわけではない。
・「浜松地区大学」の名称が「浜松医科工科大学」になると新聞報道されているが、正式決定した事実はない。「情報学部の存在感が薄くなる」ことを根拠にした反対論があることは承知している。ただし、大学の名称が単科大学的であっても、多様な研究教育に従事する優れた大学は多数ある。「名称が単科大学的であるから、大学のブランド価値が下がる」というという意見には根拠が薄いと感じている。
・浜松医科大学と静岡大学の合併については、適切なプロセスを経て、大学の意思決定機関すべての賛成を経ているものであり、手続き上の瑕疵はないと考える。なお、現状、本学の意思決定機関では静岡キャンパス所属教授が大多数を占めており、浜松キャンパスの意向が通りにくい現実がある。「意思決定のプロセスで、静岡キャンパス側の主張が軽視されている」という意見は事実と反する。
*******************
個人的には、小異を捨てて大同につき、この合併が成功裏に進み、「静岡地区大学」と「浜松地区大学」の双方ががますます発展していくことを強く願っています。
https://www.at-s.com/news/article/topics/shizuoka/675661.html
「情報学部の存在感が薄れてしまう」などの理由で反対の声もあるそうです。たしかに、理解できるところです。
浜松キャンパス学生物件、地域シェアNO.1のアライブとしても、気になるニュースです。

合併推進派の静岡大学石井学長が、個人ブログで合併について詳細に説明しています。
https://wwp.shizuoka.ac.jp/president-blog/
非常にストレート、また論理的で丁寧な説明で、このブログ全体を通して、石井学長の合併に賭ける熱意と誠意が伝わってきます。
関心のあるかたは是非直接読んでいただきたいのですが、かなりの長文なので、私の理解なりに、要約します。
*******************
・浜松医科大学と静岡大学が合併して医学部を含む総合大学となることは、教育の多様性や大学運営上の財政面で大きなメリットがある。
・2000年に全学部共通の教養課程が廃止されて以降、静岡キャンパスと浜松キャンパスは事実上別々の大学として機能しており、学生間の交流は少ない。合併により静岡大学ホールディングスの下に「静岡地区大学」と「浜松地区大学」の2大学に再編して、組織の在り方を実際の大学の実情に合わせることは、意思決定の合理化・迅速化につながる。
・合併により、「静岡地区大学」よりも、医学部を含む「浜松地区大学」のほうが財政的・規模的に大きくなるのは事実だが、合併に伴い現状の静岡キャンパスの財政や事業規模が縮小されるわけではない。
・「浜松地区大学」の名称が「浜松医科工科大学」になると新聞報道されているが、正式決定した事実はない。「情報学部の存在感が薄くなる」ことを根拠にした反対論があることは承知している。ただし、大学の名称が単科大学的であっても、多様な研究教育に従事する優れた大学は多数ある。「名称が単科大学的であるから、大学のブランド価値が下がる」というという意見には根拠が薄いと感じている。
・浜松医科大学と静岡大学の合併については、適切なプロセスを経て、大学の意思決定機関すべての賛成を経ているものであり、手続き上の瑕疵はないと考える。なお、現状、本学の意思決定機関では静岡キャンパス所属教授が大多数を占めており、浜松キャンパスの意向が通りにくい現実がある。「意思決定のプロセスで、静岡キャンパス側の主張が軽視されている」という意見は事実と反する。
*******************
個人的には、小異を捨てて大同につき、この合併が成功裏に進み、「静岡地区大学」と「浜松地区大学」の双方ががますます発展していくことを強く願っています。
常勝集団のプリンシプル
2019年10月10日
ラグビーワールドカップ、盛り上がってますね!
僕もテレビやファンゾーンで釘付けになって見ています。

ワールドカップが始まるまで、ルールを知らなかったんですが、集中的に5~6試合みると、何となく分かってきますね。
今回の日本代表は、帝京大学ラグビー部OBが多いですね。
フッカーの堀江選手、フランカーの姫野選手、スクラムハーフの流選手ほか、31名中7名が帝京OBです。
帝京ラグビー部の岩出監督の「常勝集団のプリンシプル」を読むと、OBが活躍する理由が何となくわかります。
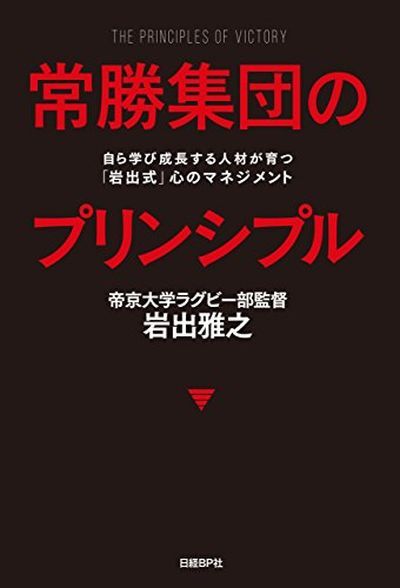
https://www.amazon.co.jp/dp/B07B8MKT34/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
以下、この本から印象的なところを抜粋します。
******************
・技術や根性、伝統だけで勝てる時代は終わった
・「自分で決める」から、やる気になる
・部下がその気になるまで辛抱強く待つことも、人材育成のマネジメントの重要な仕事
・余裕のある人が、余裕のない人の仕事を引き受けるから、組織全体にも余裕が出てくる。
・ラグビーの勝利がすべてではない。部員が卒業後、社会人となり、周囲の人たちからしっかり愛されて、信頼されて、幸せに人生を生きていけるように、ラグビーを通して人間的に成長してもらうこと。これが目標。
・失敗は成長の糧であり、進化のきっかけとなる「ありがたいヒント」
・大事なのは未来や過去ではなく「現在」
・組織文化のフレームワークは、トップが作っていく人工物であり、自然にできていくものではない
・トップの一挙手一投足は、トップ本人が思っている以上に、組織文化に重大な影響を与える
・組織文化の大敵は惰性。「去年勝てたのだから、今年もそれを繰り返せばよい」と発想した瞬間から、チームの弱体化が始まる。
・失敗を恐れて守りに入るよりも、挑戦して失敗したほうが、組織の文化やモチベーションに与えるダメージは少ない。
・圧倒的な強者だからこそ、組織の内部には惰性や油断が生まれていく。
・見えないものほど大事。見えるものはすぐに真似される。
******************

日本代表の勝利を願っています!
僕もテレビやファンゾーンで釘付けになって見ています。

ワールドカップが始まるまで、ルールを知らなかったんですが、集中的に5~6試合みると、何となく分かってきますね。
今回の日本代表は、帝京大学ラグビー部OBが多いですね。
フッカーの堀江選手、フランカーの姫野選手、スクラムハーフの流選手ほか、31名中7名が帝京OBです。
帝京ラグビー部の岩出監督の「常勝集団のプリンシプル」を読むと、OBが活躍する理由が何となくわかります。
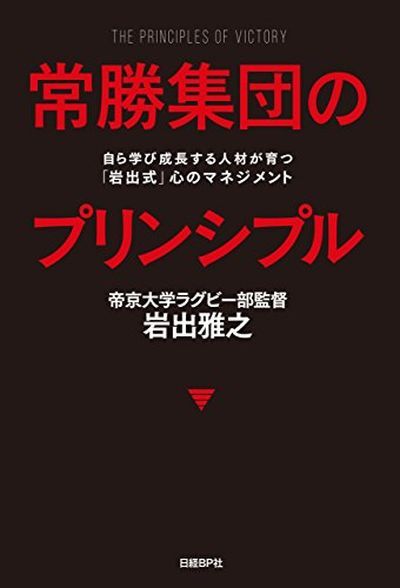
https://www.amazon.co.jp/dp/B07B8MKT34/ref=dp-kindle-redirect?_encoding=UTF8&btkr=1
以下、この本から印象的なところを抜粋します。
******************
・技術や根性、伝統だけで勝てる時代は終わった
・「自分で決める」から、やる気になる
・部下がその気になるまで辛抱強く待つことも、人材育成のマネジメントの重要な仕事
・余裕のある人が、余裕のない人の仕事を引き受けるから、組織全体にも余裕が出てくる。
・ラグビーの勝利がすべてではない。部員が卒業後、社会人となり、周囲の人たちからしっかり愛されて、信頼されて、幸せに人生を生きていけるように、ラグビーを通して人間的に成長してもらうこと。これが目標。
・失敗は成長の糧であり、進化のきっかけとなる「ありがたいヒント」
・大事なのは未来や過去ではなく「現在」
・組織文化のフレームワークは、トップが作っていく人工物であり、自然にできていくものではない
・トップの一挙手一投足は、トップ本人が思っている以上に、組織文化に重大な影響を与える
・組織文化の大敵は惰性。「去年勝てたのだから、今年もそれを繰り返せばよい」と発想した瞬間から、チームの弱体化が始まる。
・失敗を恐れて守りに入るよりも、挑戦して失敗したほうが、組織の文化やモチベーションに与えるダメージは少ない。
・圧倒的な強者だからこそ、組織の内部には惰性や油断が生まれていく。
・見えないものほど大事。見えるものはすぐに真似される。
******************

日本代表の勝利を願っています!
「日本人の国民性調査」のご紹介
2019年09月01日
最近、ちょっとした関心があって「日本人の国民性調査」結果を読む機会がありました。
調査を実施している統計数理研究所によると。。。
----------
「日本人の国民性調査」は、統計数理研究所が行っている統計調査の一つで、日本人のものの見方や考え方とその変化を、社会調査によってとらえようとするものです。
調査が始まったのは、戦後間もない1953年 (昭和28年) です。その後5年ごとに調査を繰り返し、初回から数えて60年目の2013年 (平成25年) には第13次調査を行いました。これらの調査は、基本的には同じ調査手法・同じ質問項目で実施しています。
----------
同じ調査項目で長年にわたってリサーチを続けることで、日本人のメンタリティの長期敵な変化の傾向を見ることができる、貴重な調査です。
個人的に興味深かった調査結果を二つだけ紹介します。
**************
1)日本人は年々「親切」になっている
たいていの人は『他人の役に立とうとしているか』、あるいは『自分のことだけに気をくばっているか』を尋ねたところ,"他人の役に"という人は1978年は19%に過ぎなかったが,その割合は毎回少しずつ増加し,今回2013年は前回2008年の36%から10ポイント近く伸びた45%となって,はじめて"自分のことだけ"の割合 (42%) を上回った

2)今の20代は過去最高に「未来を楽観」している
20歳代に限ると,楽観的見通しの割合は1978年よりも2013年の方が高く,例えば"ひとびとは幸福になると思う"という20歳代は2013年には42%にものぼる。

**************
いろいろとネガティブなニュースが多い昨今ですが、全体でみると、日本は着実に「いい国」になっているんですね。
この調査は2013年度に実査した結果で、2018年度版の調査レポートが近日中に公開されるとのこと。どういう結果になるか、楽しみです。
2013年度版の調査結果の詳細は、下記になります。
ご関心のある方はぜひ。
https://www.ism.ac.jp/kokuminsei/page2/index.html
調査を実施している統計数理研究所によると。。。
----------
「日本人の国民性調査」は、統計数理研究所が行っている統計調査の一つで、日本人のものの見方や考え方とその変化を、社会調査によってとらえようとするものです。
調査が始まったのは、戦後間もない1953年 (昭和28年) です。その後5年ごとに調査を繰り返し、初回から数えて60年目の2013年 (平成25年) には第13次調査を行いました。これらの調査は、基本的には同じ調査手法・同じ質問項目で実施しています。
----------
同じ調査項目で長年にわたってリサーチを続けることで、日本人のメンタリティの長期敵な変化の傾向を見ることができる、貴重な調査です。
個人的に興味深かった調査結果を二つだけ紹介します。
**************
1)日本人は年々「親切」になっている
たいていの人は『他人の役に立とうとしているか』、あるいは『自分のことだけに気をくばっているか』を尋ねたところ,"他人の役に"という人は1978年は19%に過ぎなかったが,その割合は毎回少しずつ増加し,今回2013年は前回2008年の36%から10ポイント近く伸びた45%となって,はじめて"自分のことだけ"の割合 (42%) を上回った

2)今の20代は過去最高に「未来を楽観」している
20歳代に限ると,楽観的見通しの割合は1978年よりも2013年の方が高く,例えば"ひとびとは幸福になると思う"という20歳代は2013年には42%にものぼる。

**************
いろいろとネガティブなニュースが多い昨今ですが、全体でみると、日本は着実に「いい国」になっているんですね。
この調査は2013年度に実査した結果で、2018年度版の調査レポートが近日中に公開されるとのこと。どういう結果になるか、楽しみです。
2013年度版の調査結果の詳細は、下記になります。
ご関心のある方はぜひ。
https://www.ism.ac.jp/kokuminsei/page2/index.html
「はままつ仕事図鑑」創刊になりました
2019年08月01日
浜松の魅力ある職場を紹介した「はままつ仕事図鑑」が創刊になりました。

(「はままつ仕事図鑑」特設ページ)
https://shigoto-hm.com/
谷島屋さんの各店で平積みになっています。

通読して、浜松には、ほんとうに魅力的な職場がたくさんあるなーと改めて思います。
同じ価値観をもった仲間と一緒に働ける、自分の仕事が世の中の役に立っていると実感できる、家庭とバランスよく仕事ができる、フェアな報酬だと感じられる、自分の持ち味を発揮できる・・・
だれしも、こういう職場で働きたいですよね。僕もそうです。
少子高齢化、人手不足の今だからこそ、「いい職場づくり」で経営者は必死になって競争するべきだし、それが合理的だ、と結構真面目に思っています。
理想の職場までの道のりはまだまだ遠いですが。。。
でも、一歩一歩進んでいくことが大事だと自分に言い聞かせてもいます。
「はままつ仕事図鑑」、アライブの社員も登場しています。
ぜひ谷島屋さんでお手に取ってみてください。

(「はままつ仕事図鑑」特設ページ)
https://shigoto-hm.com/
谷島屋さんの各店で平積みになっています。

通読して、浜松には、ほんとうに魅力的な職場がたくさんあるなーと改めて思います。
同じ価値観をもった仲間と一緒に働ける、自分の仕事が世の中の役に立っていると実感できる、家庭とバランスよく仕事ができる、フェアな報酬だと感じられる、自分の持ち味を発揮できる・・・
だれしも、こういう職場で働きたいですよね。僕もそうです。
少子高齢化、人手不足の今だからこそ、「いい職場づくり」で経営者は必死になって競争するべきだし、それが合理的だ、と結構真面目に思っています。
理想の職場までの道のりはまだまだ遠いですが。。。
でも、一歩一歩進んでいくことが大事だと自分に言い聞かせてもいます。
「はままつ仕事図鑑」、アライブの社員も登場しています。
ぜひ谷島屋さんでお手に取ってみてください。
賃貸経営応援セミナー 開催しました
2019年07月02日
6/23に、本年度第一回目の賃貸経営応援セミナーを実施しました。
「この春に行った生の空室対策とテナントリテンションについて」と題し、
参加された25組30名のオーナー様と一緒に賃貸経営のありかたを議論し、
またアライブの取り組みをお伝えしました。

結局のところ、賃貸経営は
1)いい部屋を作って、しっかりと情報発信して、良い人に入居してもらう
2)入居者には快適に暮らしていただき、できるだけ長く住んでもらう
の2つに尽きる、と我々は考えます。
そのための地道な取り組みを、飽きずにどれだけ真面目にやれるか、が勝負です。
もっとも、
「どういう物件を、いくらで購入するか(新築するか)」
「金利をいくらで借りるか、どれだけ自己資金を入れるか」
も極めて重要なのですが。。。
これらは、賃貸経営をスタートする前に徹底的に考えるべき問題です。
賃貸経営がスタートした後は、当たり前のことを、地道に精度高く取り組み続けることに、一番価値がある。
我々は、こういう考え方で、(地味ですが)かなりまじめに賃貸経営に取り組んでます。
次回は8月にセミナー開催します。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
「この春に行った生の空室対策とテナントリテンションについて」と題し、
参加された25組30名のオーナー様と一緒に賃貸経営のありかたを議論し、
またアライブの取り組みをお伝えしました。

結局のところ、賃貸経営は
1)いい部屋を作って、しっかりと情報発信して、良い人に入居してもらう
2)入居者には快適に暮らしていただき、できるだけ長く住んでもらう
の2つに尽きる、と我々は考えます。
そのための地道な取り組みを、飽きずにどれだけ真面目にやれるか、が勝負です。
もっとも、
「どういう物件を、いくらで購入するか(新築するか)」
「金利をいくらで借りるか、どれだけ自己資金を入れるか」
も極めて重要なのですが。。。
これらは、賃貸経営をスタートする前に徹底的に考えるべき問題です。
賃貸経営がスタートした後は、当たり前のことを、地道に精度高く取り組み続けることに、一番価値がある。
我々は、こういう考え方で、(地味ですが)かなりまじめに賃貸経営に取り組んでます。
次回は8月にセミナー開催します。
ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
社員旅行に行ってきました
2019年06月05日
アライブでは、隔年で2泊3日の社員旅行をしています。
今年は沖縄班と金沢班。僕は金沢班で参加しました。
金沢を観光するのは初めてで、見どころがたくさんありました。




人口は46万人と浜松市よりもだいぶ少ないのですが、中心市街地は浜松よりもずっとにぎやかでした。
あと、とにかく美術館・博物館が多い!金沢21世紀美術館を代表に、金沢能楽美術館、石川近代文学館、石川県立美術館、石川県立歴史博物館、鈴木大拙館、泉鏡花記念館・・・と一日ではとても回り切れない。
https://4travel.jp/domestic/area/hokuriku/ishikawa/kanazawa/kanazawashinai/museum
歴史と文化の厚みがある街でした。
一方、僕は職業病で、観光で違う街に行くと、必ずコンビニの求人誌を見て求人の数と質をチェックするのですが。。。求人は浜松の方がずっと多かったです。時給も、正直浜松のほうが高い。
浜松は良くも悪くも仕事をする街なんだな~と改めて思います。
観光力では金沢に完敗ですが、日々を暮らしていくには、やっぱり浜松ですね。
今年は沖縄班と金沢班。僕は金沢班で参加しました。
金沢を観光するのは初めてで、見どころがたくさんありました。




人口は46万人と浜松市よりもだいぶ少ないのですが、中心市街地は浜松よりもずっとにぎやかでした。
あと、とにかく美術館・博物館が多い!金沢21世紀美術館を代表に、金沢能楽美術館、石川近代文学館、石川県立美術館、石川県立歴史博物館、鈴木大拙館、泉鏡花記念館・・・と一日ではとても回り切れない。
https://4travel.jp/domestic/area/hokuriku/ishikawa/kanazawa/kanazawashinai/museum
歴史と文化の厚みがある街でした。
一方、僕は職業病で、観光で違う街に行くと、必ずコンビニの求人誌を見て求人の数と質をチェックするのですが。。。求人は浜松の方がずっと多かったです。時給も、正直浜松のほうが高い。
浜松は良くも悪くも仕事をする街なんだな~と改めて思います。
観光力では金沢に完敗ですが、日々を暮らしていくには、やっぱり浜松ですね。
Posted by
不動産のアライブ
at
09:00
賃貸マンション経営の実態
2019年05月11日
不動産会社で仕事をしていると、ときどき
「人口が減っていく中で賃貸マンション経営って大丈夫なんですか?」
という質問を受けることがあります。
新卒採用の現場で、学生さんから聞かれることもあります。
直感的には、人口が減れば空室も増えて、賃貸マンション経営は厳しくなるように思えます。
一方で、アライブの管理物件の入居率は上がっており、お任せいただく管理物件も増えています。

また、今年の2月~3月に須山建設の設計・施工で浜松駅周辺に4棟・67戸の新築賃貸マンションを一度にお引渡ししました。これらの物件も、3月末までにすべて満室になりました。
■浜松駅周辺の新築物件(須山建設)
https://www.gankooyaji.jp/blog/cat61/
https://www.gankooyaji.jp/blog/cat54/
https://www.gankooyaji.jp/blog/cat53/
https://www.gankooyaji.jp/blog/cat52/
現場の実態としては、賃貸マンションの経営環境は決して悪くない。
このギャップをどう考えればいいのか?
***********
考えられる要因をいくつかリストアップしてみます。
1)人口は減っているが、世帯数は増えている
浜松市の世帯数は、
2016年5月…329,385世帯
2017年5月…332,505世帯
2018年5月…335,838世帯
2019年5月…339,265世帯
と、毎年およそ3000世帯ずつ、着実に増えています。人口は微減していても、それ以上ペースで単身化・核家族化が進んでいるんですね。世帯数が増えている限り、賃貸マンションのニーズは根強くある。
2)今のお客様が求めるレベルの部屋は不足している
5/11現在、SUUMO上には浜松市中区の2LDKは「8,889件」募集されています。
ただし、「バストイレ別、駐車場、エアコン、室内洗濯機、シャワートイレ、追い炊き、モニターホン」を条件にすると、「3,103件」になってしまう。
これらの設備は、今のお客様にとってはほぼ必須の条件です。そうすると、「8,889件-3,103件=5,786件」は、最初から選考外の物件、ということになります。
空室の65%以上は、「当たり前にやるべき空室対策」をやっていないわけです。
逆に言えば、当たり前の設備グレードアップをやるだけで上位35%に入ることができるし、そうすればキチンと入居者を見つけることはそれほど難しくない。
これは、管理会社の仕事です。オーナー様に、今の入居者のニーズをしっかりと説明して、やるべきリフォームをしっかりやって、選ばれる部屋を作る。こういう当たり前のことをやれている会社は、意外なほど少ないように思います。
***********
最近、大手企業の賃貸住宅に関する不祥事が続いています。思うに、賃貸マンション経営というのは本質的に地道な、地域密着でコツコツとやるべき仕事です。地域ごとに経済環境も都市の成り立ちも異なるにも関わらず、効率優先で全国一律で建物とサービスを展開して、現場のニーズとのギャップはサブリースの仕組みで埋めていく。。。という発想に無理があるように思う。
ミドルリスク・ミドルリターンの長期資産運用として、賃貸マンション経営の魅力とリスクが正しく認識されることを願っています。
「人口が減っていく中で賃貸マンション経営って大丈夫なんですか?」
という質問を受けることがあります。
新卒採用の現場で、学生さんから聞かれることもあります。
直感的には、人口が減れば空室も増えて、賃貸マンション経営は厳しくなるように思えます。
一方で、アライブの管理物件の入居率は上がっており、お任せいただく管理物件も増えています。

また、今年の2月~3月に須山建設の設計・施工で浜松駅周辺に4棟・67戸の新築賃貸マンションを一度にお引渡ししました。これらの物件も、3月末までにすべて満室になりました。
■浜松駅周辺の新築物件(須山建設)
https://www.gankooyaji.jp/blog/cat61/
https://www.gankooyaji.jp/blog/cat54/
https://www.gankooyaji.jp/blog/cat53/
https://www.gankooyaji.jp/blog/cat52/
現場の実態としては、賃貸マンションの経営環境は決して悪くない。
このギャップをどう考えればいいのか?
***********
考えられる要因をいくつかリストアップしてみます。
1)人口は減っているが、世帯数は増えている
浜松市の世帯数は、
2016年5月…329,385世帯
2017年5月…332,505世帯
2018年5月…335,838世帯
2019年5月…339,265世帯
と、毎年およそ3000世帯ずつ、着実に増えています。人口は微減していても、それ以上ペースで単身化・核家族化が進んでいるんですね。世帯数が増えている限り、賃貸マンションのニーズは根強くある。
2)今のお客様が求めるレベルの部屋は不足している
5/11現在、SUUMO上には浜松市中区の2LDKは「8,889件」募集されています。
ただし、「バストイレ別、駐車場、エアコン、室内洗濯機、シャワートイレ、追い炊き、モニターホン」を条件にすると、「3,103件」になってしまう。
これらの設備は、今のお客様にとってはほぼ必須の条件です。そうすると、「8,889件-3,103件=5,786件」は、最初から選考外の物件、ということになります。
空室の65%以上は、「当たり前にやるべき空室対策」をやっていないわけです。
逆に言えば、当たり前の設備グレードアップをやるだけで上位35%に入ることができるし、そうすればキチンと入居者を見つけることはそれほど難しくない。
これは、管理会社の仕事です。オーナー様に、今の入居者のニーズをしっかりと説明して、やるべきリフォームをしっかりやって、選ばれる部屋を作る。こういう当たり前のことをやれている会社は、意外なほど少ないように思います。
***********
最近、大手企業の賃貸住宅に関する不祥事が続いています。思うに、賃貸マンション経営というのは本質的に地道な、地域密着でコツコツとやるべき仕事です。地域ごとに経済環境も都市の成り立ちも異なるにも関わらず、効率優先で全国一律で建物とサービスを展開して、現場のニーズとのギャップはサブリースの仕組みで埋めていく。。。という発想に無理があるように思う。
ミドルリスク・ミドルリターンの長期資産運用として、賃貸マンション経営の魅力とリスクが正しく認識されることを願っています。
e-bikeで浜名湖一周してきました
2019年04月02日
先日、浜松駅前の「浜松魅力発信館 The GATE HAMAMATSU」で、ヤマハ発動機製の最新式電動アシスト自転車をレンタルして、浜名湖一周してきました。


2年前に普通の自転車で浜名湖一周した時はかなり疲労困憊でしたが、今回は電気の力を借りて楽しく散歩気分でサイクリングできました。テクノロジーの進歩はすごい!
カタログスペックではバッテリーの持ちは109kmですが、約100km走って70%ほどの電力消費と、カタログ以上の性能をみせてくれました。


従来の電動アシスト自転車は、買い物や通学通勤を目的としたシティサイクルでしたが、この数年、大容量バッテリーを搭載したスポーツサイクルが「e-bike」としてヨーロッパを中心に急速に発展を遂げているそうです。
30万円前後とお値段は相当ですが、一日乗ると売れている理由が分かる優れモノでした。